塾では聞かせてもらえない、「この国語の解答をしていたらまずい!」とその解決法を5分で。
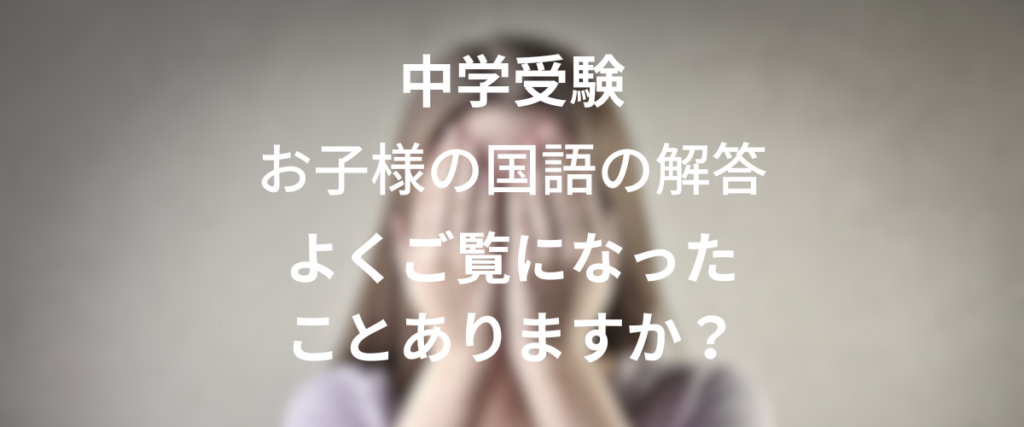
①わが子が不思議な答えを書いてくる原因と解決法
子供はもともと問題に答えようという気があまりなく(何か書けばいい程度の感覚)、しかも何を書いていいのかわからないところに、
「文中に書いてあることを答えよう」と塾で授業中に習う、または習っている気がしているので、下のように答える子が続出します。

ともきはなぜ朝お祭りに行くことをやめてしまったのか。

ふとんから出られなかったから。
おそらく本文に「ふとんから出られなかった」と書いてあったんでしょうね。
だからそう答えた と。
ここで欠けているのは
問題は聞く価値のあることがそこにあるからこそ出すんだということに対する理解です。
普段の会話を考えてみてください。
「なんで行かなかったの?」
「起きられなかったから」では、
「なんで起きられなかったの?」とか
「具合悪かったの?」「寝不足だったの?」
とかっていう次の質問が出てくる可能性がありますよね。
テストでも日常会話と同じでこれではだめなんです。
採点する人は答えた生徒にさらに質問することはできませんから。
答えを読んだ人がそれ以上質問せずに納得できる、
疑問を解消する答えが必要なんです。
この場合だと、
「前日にかなに言った言葉がひどいものだったと思って申し訳なくなり、会いにくさを感じていたから。」
などといった答えです。
ふとんから出られなかったという部分は、本文を読めば誰でもわかることなので、むしろ答える必要がないくらいなんです。
下線を引いた部分は本文には通常直接そのままの表
現で書いてはいなくて、本文から読み取るべき部分なんですね。
この「本文から読み取る」と「本文から抜き出す」の違いはとても大きいんです。
考えたプロセスをほめる
子供は基本的に勉強を自分の意志で毎日やっているのではありません。
(自分から塾に行きたいと一回言ったことがあってもです。
友達が行ってるらしいからくらいのことで、そんなに断固たる決意を持って言ったわけではありません。)
「勉強の価値」も大人にいくら説明されたとしても、人生経験の全くない小学生が心の底から理解できるようなものではありません。
みなさんだって勉強が必要だと強く思ったのはもっとずっと後ですよね?
子供は程度の差こそあれ、全員自分の毎日の生活に一番影響を与える親の視線、自分に対する評価を意識して勉強を日々しています。
だから親御さんが「正解をしなくてはいけない、正解しないと怒られたり悲しまれたりする」という呪縛から子供を解き放ってあげることがとても重要です。
正解したことでなく、仮に答えが見当違いでも、子供が文章を読んでしっかり考えたことを両親が口に出してほめると、不正解を恐れて「なんでも文章中から抜き出す」状態から子供が脱却する大きなきっかけになります。
不正解を恐れると、自分で文を考えると✕になりやすいという発想になり、無難に文中から抜き出そう→思考停止 ということになりやすいんです。
子供の不正解に対して「なんでこんなミスをするの!よく読みなさい!」というのではなく、
よく読む=書かれていない気持ちや状況を書かれていることから推測すること なんだというのを伝えてあげると子供は文を読んで頭を働かせるようになりやすいです。
②日常生活の時の読解力を机の上でも出せれば、今よりもっと文章が読めて、正解もできるようになる。
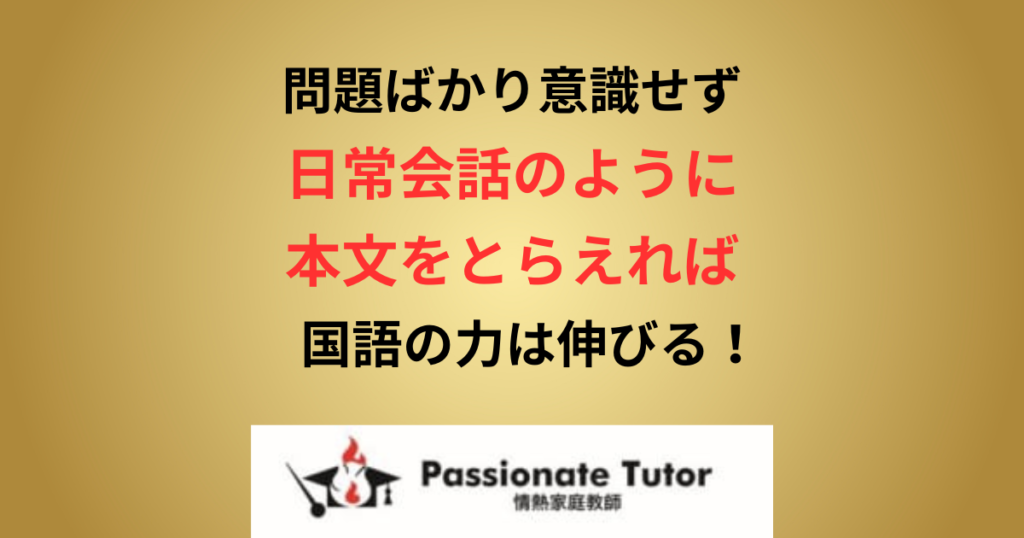
問題に対して本文から抜き出しをしてしまうことがおかしな解答をしてしまう大きな原因だということを述べましたが、
実は「正解をするための力」はすでに子供たちの中にあることが多いんです。
例えばお子さんと遊園地に行くと
「次はお化け屋敷に行こう」
「なんで?さっきジェットコースターに乗るって言ってたのに。」
「もう昼ご飯の時間だからあんまり長く並ぶ乗り物は今は乗れないよ。」
「わかったー😑」
という風にちゃんと発言の理由まで気にしてるはずなんです。
この理由を考える力を、目の前の文章に対しても発揮できるように子供を導くことができれば、
特別なコツの暗記などしなくても文章の読解力が上がり、問題に答えられるようになります。
それを塾に通って何か国語のテストに特有な「答え方」があるんだと誤解を重ねて、逆に問題に答えらえなくなっている生徒を何人も僕は見てきました。
国語のテストは一般に思われているよりずっと日常必要なコミュニケーションや自然な読解の力を問うているもので、テクニック的なものを身につけているかを試しているものではないんです。
抜き出し問題なんてものもありますが、
それだって本来文を書いて子供に答えさせたいところを、採点の手間がかなりかかってしまうことなどから仕方なく出しているにすぎないもので、
「抜き出す力」を問うているわけではないんです。

でも、国語のテストっていろいろな出題形式があるよね?
志望中学ごとでも差はあるっていうし・・・
文章を読んでそこにある情報から「考える」ことさえできるようになっていれば、抜き出し、記号選択などという出題形式の多少の違いにはすぐに適応できるようになりますから心配いりません。
それではこの記事のまとめです。
この記事のまとめ
読解力を上げて、国語のテストでの解答力をあげるには、
①子供に正解を求めずに、文章を読んで登場人物の気持ちや状況を推測させる(✕ぬき出し)ようにする。
②子供の考える姿勢を評価しほめる。
💡国語の学習=子供の持っている普段の会話の時に発揮される相手の気持ちや置かれた状況を考える力を、目の前の文章に対しても発揮できるようにすること。
関連記事はコチラから↓↓↓


