
TOEIC対策
case1:450点→645点、指導期間9か月
英語はかなり嫌いで、勉強にも相当抵抗感がある生徒さんでしたが、毎週少しづつ話せる英語が増え、手応えが出てくることで家庭での学習時間も毎日2時間近くまで増加。
①授業中は幸い文法の飲み込みは早かったので説明は短めにし、実際に口に出す練習をたくさん授業中に行った。
②家庭学習では主に指定のアプリ学習で50問、文法演習30分、TOEIC会話文暗唱に日々取り組んでいただいた。目標600点のところ見事645点を獲得。
case2:530点→775点、指導期間3年
月に2回の指導で大学生活をエンジョイしながらのトライでしたが、
順調に少しづつ得点を伸ばし775点に到達。①授業中は文法の理屈の指導を丁寧におこない、
TOEICで出題される文の中で構造のわからない文を着実に減らしていった。
②家庭学習では主に単語アプリ学習50問、授業の復習30分、TOEIC会話文暗唱に日々取り組んでいただいた。
発音や会話力にも自信が増し、現在は外資系の就職も視野に入れている。
case3:230点→615点、指導期間3年
中学時から勉強は大の苦手で、成績表の1を減らすことからスタートした生徒さん。
多くの科目を無理して勉強し大学受験で苦しむよりも推薦でも就職でも直接役立つTOEICを、と私が提案し、
高2よりTOEIC対策を早期開始。長い説明を理解するのは苦手だったので、
①授業中は文法の説明は最小限にとどめ、ロールプレイングや反復を重視。
②家庭学習では主に単語アプリ100問、授業の復習1時間に日々取り組んでいただいた。
発音が良くなったことも英語への前向きな気持ちにつながり、
英語の推薦で入った大学でもすきま時間に学習を続け615点を獲得。
就職活動でも面接で英語学習を努力したこととして話し内定につなげる。
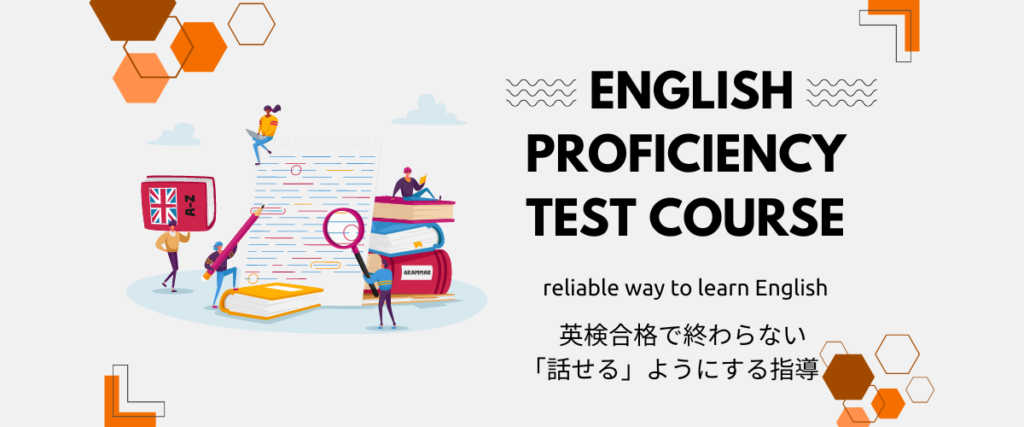
英検対策
case1:英検準2級から2年で準1級(高校英語教師平均レベル以上)へ
英語も勉強も少し苦手な高1という状態からスタート。アプリでの単語学習を確立することから始め、語彙数を2500から6500に伸ばす。
大学受験の長文読解問題も使いながらリーディングの力もアップ。ライティングとスピーキングの対策は、私が1級を取得した時と同じやり方で授業中に同時に行い、特に壁にぶつかることもなく順調に実力アップ。結果リスニング力は自然と伸びた。
スピーキング力は授業中も家庭学習でも常に扱った文は空で言えるようにしたおかげで、大学入学時すぐ企業のインターンシップに参加し、
海外の方ばかりの中で営業戦略について議論できるまでになった。
case2:英検3級から1年半で英検準2、2級合格へ
勉強は比較的得意な高1の生徒さん。家庭学習では主に、アプリ学習は馴染まなかったので単語カードを使っての語彙力強化、リスニング文の暗唱、学校の英語の教科書の暗唱を行った。
授業では発音指導、文法解説が主。直前期はライティング指導や面接指導が主となった。
たくさん勉強はしたが、結果大きく苦しむことなく2級突破まで到達。
case3:英検3級から1年で英検2級合格
勉強が得意な高1の生徒さん。
家庭学習がとにかく嫌いだったので、ますは授業中に私が必須と思っている文法事項を繰り返し質問し定着させた。
また語彙についても、最初は授業中にアプリや単語集を使いながら増やしていった。
3か月くらいたったところから本人の意欲が増し、家庭学習を増やしていきライティング、リスニング、スピーキングの力をつけた。
リーディングに関しては最後まで家ではあまり勉強しなかったので、授業中に取り組んで最低限の演習量を確保した。
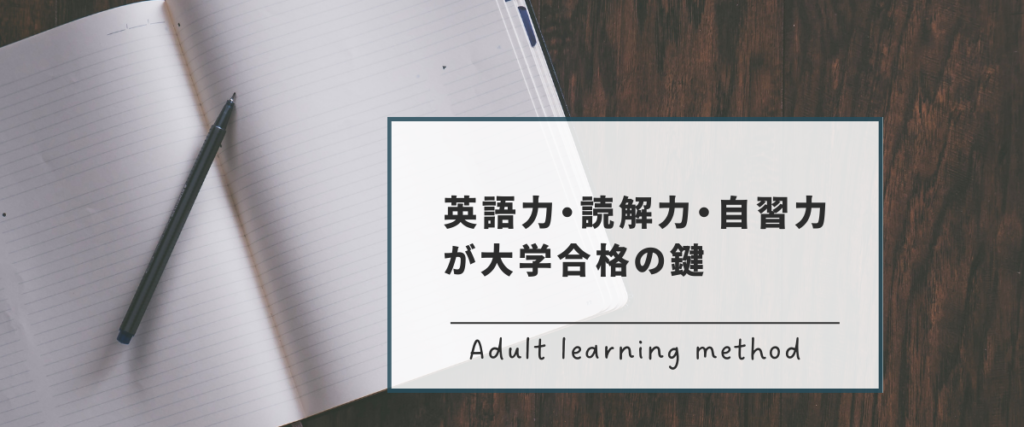
大学入試対策
case1:マイペースで勉強し早稲田大学社会科学部へ
もともと学力の高かった生徒、ただ英文法に少し難があり、英語の成績は少し悪かった。
授業中は文法指導→それをつかった英作文を中心に。単語学習はあまり積極的に行わなかったので、速読英単語を中心とした丸暗記を避けた学習方法で。
英語長文読解は授業中の指導と演習量を積むに従って順調に得点アップ。1年間の指導で他教科の出来ももともとよかったせいもありスムーズに合格。
case2:努力が花開き中央大学総合政策学部へ
定期テスト勉強以外はした経験のない生徒、模試でも英偏差値40、国30ほど。日本史を選択し、セオリーとは逆に日本史から学習を開始。
家庭での日本史学習が軌道に乗るように授業中も指導。その後英語を中心とし、最終的には得意科目に。偏差値は63~72ほどに。(模試の種類による)。
国語は最も苦手だったので直前期に集中して授業を行い、共通テスト本番では小説パート94%の得点を取るまでに。猛勉強が実り見事中央大学総合政策学部に合格。
case3:直前指導で法政大学デザイン工学部へ
直前期3か月の指導。
共通テスト英語過去問では65%ほどからのスタート。
長文読解を徹底的に指導し、40%ほどの得点から90%近くまで伸ばした。本番は英語85%得点。
各大学個別入試軒並み80%を超える正解率で(私が持ち帰った問題をもとに採点しました。)英語が合格の原動力に。
化学の学習アドバイスも行い2か月で偏差約25アップ。(本番は振るいませんでしたが)
合格大学一覧
早稲田大学社会科学部、中央大学総合政策学部、経済学部、
明治大学政治経済学部、経営学部、法政大学デザイン工学部、経営学部、
青山学院大学文学部、東京都市大学理工学部、デザイン学部、
東京電機大学工学部、理工学部、システムデザイン工学部、他多数。
(無謀なところに第一志望を設定させないせいもありますが、指導したほぼ全員が第一志望に合格しています。)

長期指導
case1:大手塾を3つ渡り歩いた小学生時代→私立中高でも成績上位で大学も第一志望へ
中学受験を見据えて大手塾に通ったものの集団授業についていけず、個別指導を受けるも成績は全く上がらず、家庭教師の先生とも合わず、そんな折私のところにきた生徒さんでした。
社会→算数→理科→国語の順で一緒に勉強をし、家庭学習の仕方を伝えていきました。
もちろん子供が最初から家で進んで長時間勉強するわけもなく、勉強をする理由を話したり、学校生活や友達との関係について話を聞いたりアドバイスをしたり(いじめにも少しあっていたようです)勉強内容以外のことでもたくさんコミュニケーションを取りました。
(それを許してくださったご理解あるご両親には本当に感謝しております。)
そうしているうちに次第に家庭でも学習ができるようになり、授業で学んだ問題、内容の解き直し、見ずにノートに再現を主にやってもらい、中学受験も第一志望を突破、
中学でも自習の仕方を中心に教え、いつしか中学の学校の勉強はほぼ一人で学習できるようになり、彼女の時間にも余裕が生まれるようになりました。
そこからさまざまなチャレンジを行うようになり、積極性も身に着け、
大学受験時には私に提出してもらったノート(各学部の学費、履修内容、進路などを自分で調べて書いたノート)をもとに親御さんに希望の進路の説明をし、
受験勉強をし(時にさぼってもいましたが)見事第一志望合格を勝ち取りました。
case2:引っ込み思案の小5が人前で英語を話し、舞台のど真ん中に立つ高校生に
出会ったときは、学校の漢字テストもぼろぼろで計算問題すら半分も合わない状態で、何をするにも自信がなさそうなおとなしい5年生でした。
また、家庭全体に「勉強って難しくて結局なかなかできるようにはならないものだ」という空気が漂っていて、私が指導の目標を語ってもあまり真剣に受け取ってはもらえない状態でした。
しかし、その分目先のテストの結果を追わなくて良い環境であり、小学校時代はひたすら中学での学習の基礎作り(英語学習や数学の簡単な簡単な先取りなど)に時間を使うことができました。
その結果進んだ付属中学では初めて勉強についていけるようになり、自主的に勉強する気持ちが生まれてきました。勉強はまだまだ苦労することが多かったのでほぼ全教科テコ入れをしていましたが、
学校での人間関係などについても授業中に話し合い、次第に積極的に友達を引っ張ることも増えました。
そして迎えた高校生活では私が関わらなくてもそれなりについていける科目が増え、
好きなよく勉強した科目はクラストップに迫ることも出てきました(私はあまり無理強いはしないので悪い教科も出ますが)。
何より文化祭などではガンガン前に出る目の輝きの違う生徒に変わりました。
case3:あまりに苦しい中学受験塾での小学生時代→楽しい高校生活と大学進学へ
いわゆるグレーゾーンの生徒さんでした。
小5で漢字をノートに練習するにも見ながら書いても3つとお手本通りに書けず、計算もぼろぼろ。
当然進学塾の内容についていけるわけもなく、メンタル的にも悪い状態でした。お父様も現状を受け入れたくない様子で、家庭の中も雰囲気はよくありませんでした。
そんなところからの指導開始でしたが、入試に出るところをまんべんなく教えるのではなく、
今できることに集中した指導+お母様の多大な協力
による家庭学習ですこしづつできることを増やし、私立中学にも合格。
中学ではすぐに楽しい日々とはいかず、苦しい思いもたくさんしましたが、私ともたくさん話し、なんとか心折られず過ごすことができ、勉強も決定的な遅れを取らないようにすることができました。
高校に上がると今までの取り組みが花開き、自分で定期テストの勉強をするために自分が書けなかった分のノートをクラスメイトと意思疎通して自主的に借りてきたり、
数学の問題集に毎日少しづつ取り組んだりできるようになります。
小6で九九にも苦戦していた彼が、高校では2次関数や三角比のテストで70点近くとれるまでに成長しました。(もちろん教えてはいますが)
そしてなにより笑顔で高校に通えるようになり、休日に遊ぶ約束をする友達もできるようになりました。

中学入試対策
case1:記述問題を克服し麻布中学に合格
考える力はあるが、第一志望の麻布のような長い記述問題になると文の構成を意識できていない小6の生徒さん。
覚えていることをそのまま書こうとする様子も見受けられました。
授業中は①覚えていることを書くのではなく、聞かれたことに答える。
②自分の文を見たときに採点者が納得してくれるかどうか。(自分の答案を客観的に見る)をはじめとする塾では指摘されたことのないいくつかのポイントを意識してもらって演習を重ねた。
また、ご両親は塾通いに加えて、家にいるときも受験前だからと1日中勉強していないと不安を感じ、子供を注意するような状態だったので、
そのような接し方をするとやっているふりをする習慣だけがついてしまうし、毎日への意欲を失ってしまう、中学入学後にも悪影響があることを丁寧に伝えた。
その結果、子供の表情も明るくなり、間違いを恐れずじっくり考えて答案が書けるようになり、かなり緊張するタイプでありながらも本番でも力を発揮。第一志望を射止めた。
case2:なんとなくの読解を脱却し女子学院中学に合格
小6の国語は得意だが論理的に考えるところまでは行っていない生徒さんでした。
記述する際に考える点を整理し、それを毎回欠かさず意識することで、答案の質のブレをなくし、常に一定以上の内容の答案を書けるように指導していきました。
また、算数では塾で覚えた解法をひたすらあてはめて解き、途中式や図を書けと言われると手が動かない状態だったので、
①答案に書く考えは完璧に出来上がっているものである必要はない。②説明とはひたすら式を書くことではなくて文を書くこと。
といったことを意識してもらい、簡単に答えまでたどり着けない問題でも答案が書けるようにしました。
また精神的な面では、やはりご両親が過熱しすぎるところがあり、(夜の11時からでも授業をしてほしいといわれるようなことがあった)、女子学院以外への進学は考えられないといった感じだったので、
ほかにも充実した学生生活を送れる学校はあることや、精神的、体力的に余裕を持った状態で受験勉強を進める大切さを繰り返しお伝えした。
最終的には第一志望の女子学院に合格。人生初の受験を笑顔で終えることができた。
case3:ゼロからの全教科指導で東京女学館合格
当初は3年間大手塾に通っていたにもかかわらず、4教科ともにほとんど受験生としての知識はなく、比較的レベルの落ちる模試でも偏差値40に遠く及ばないところからのスタート。
答えにバツを付けられるのが苦手で指摘に弱く、うつむきがちで、ひたすら退塾しないように腫れ物に触るような扱いを受けてきた様子。
私のところでは、まず勉強は知らないことや間違っているところを探してやるものだというところから説明し、
バツをつけられてもしょんぼりしない練習(^^♪からスタート。
次第に指摘にも慣れ、くやしさを表現したり、そこからできるようになったときの喜びを感じることができるように。
算数が好きだったのでそれを中心に教え「できる自分」を感じられる時間が長くなるように工夫をした。
鍵となる家庭学習も、まずはやりやすい漢字学習や社会からできるようにし、
理科の知識中心の分野、算数の何度もやった問題、過去問の授業中扱った問題の復習など自習の成り立つものを増やしていった。
本番では緊張から腹痛に襲われ保健室受験になるアクシデントなどもあったが、2回目で第一志望に見事合格。
合格中学一覧
開成、麻布、駒場東邦、海城、渋幕、栄東、市川、芝、開智、東邦大東邦、
女子学院、鴎友、立教新座、明大付属明治、東京女学館、明大中野、法政大学中、国学院久我山、
東京都市大付属、恵泉、共立女子、実践、他多数。
受験勉強中の家庭の幸せや入学後の生徒の学習の辛さなどを考え、無謀な志望校選定を勧めていないこともあり、9割以上が第一志望に合格し、
その後も楽しく学校に通っています。(指導継続や食事を一緒にしたりしてお話を実際に聞いています。)

読解力指導
case1:1年あまりの指導で自習力大幅アップ、希望の進路の発見も
高校1年の夏からの1年あまり、他の勉強の指導をやめ、様々な仕事に関する本を題材に読解力のアップに取り組んだ。
授業中はまずは飛ばさず読むことからスタートし、次第に1文と1文のつながりを考え、段落の構成を意識して読むように指導していきました。
彼は「今まではやばかったわ。」と授業中に何度もつぶやき、指導開始3か月後からは参考書を使った英語、日本史の自習を開始。初めて勉強らしい勉強を一人でできるように。
読解練習をしていく中で、先生になりたいという進路の希望も出てくるように。ますます読み取ったことを人にわかるように伝えようという姿勢に磨きがかかり、自習力も大幅にアップ。
高2秋からの大学受験指導でも高1で理解力に大幅に磨きをかけたおかげで、学習時間に比例して順調に学力が順調に伸びるようになった。
case2:勉強に強い苦手意識があった社会人の方がITパスポート取得
読解力に不安があり、仕事をしていても同僚との仕事の飲み込みの差に悩んでいるという社会人の方。資格取得にも取り組んだことがあるが参考書の内容が全く頭に入らないとのこと。
話し合った結果ITパスポートの取得を目指しながら読解力向上を目指すことに。
一つ一つの説明を読んでいる時もどの章のどこを読んでいるのかを常に意識する、「全体像を忘れない読み方」を中心に指導をしたところ、
3か月後ごろには大枠と細部の区別がはっきりつくようになり、一読した時の理解度もアップ。スムーズな資格取得につながった。
